【連載】感情の時代をどう生きるか──現代社会の課題と感情史の可能性(前編)
技術の発展とそれを受けたメディア・社会の変化により、人々の感情がどのようにハックされ、どのような影響を受けているのかを明らかにしようとする連載シリーズ「感情ハック」。第二弾では、歴史を感情という観点からとらえ直そうとする「感情史」を研究されている、東京外国語大学の小野寺拓也先生にお話をうかがいます。
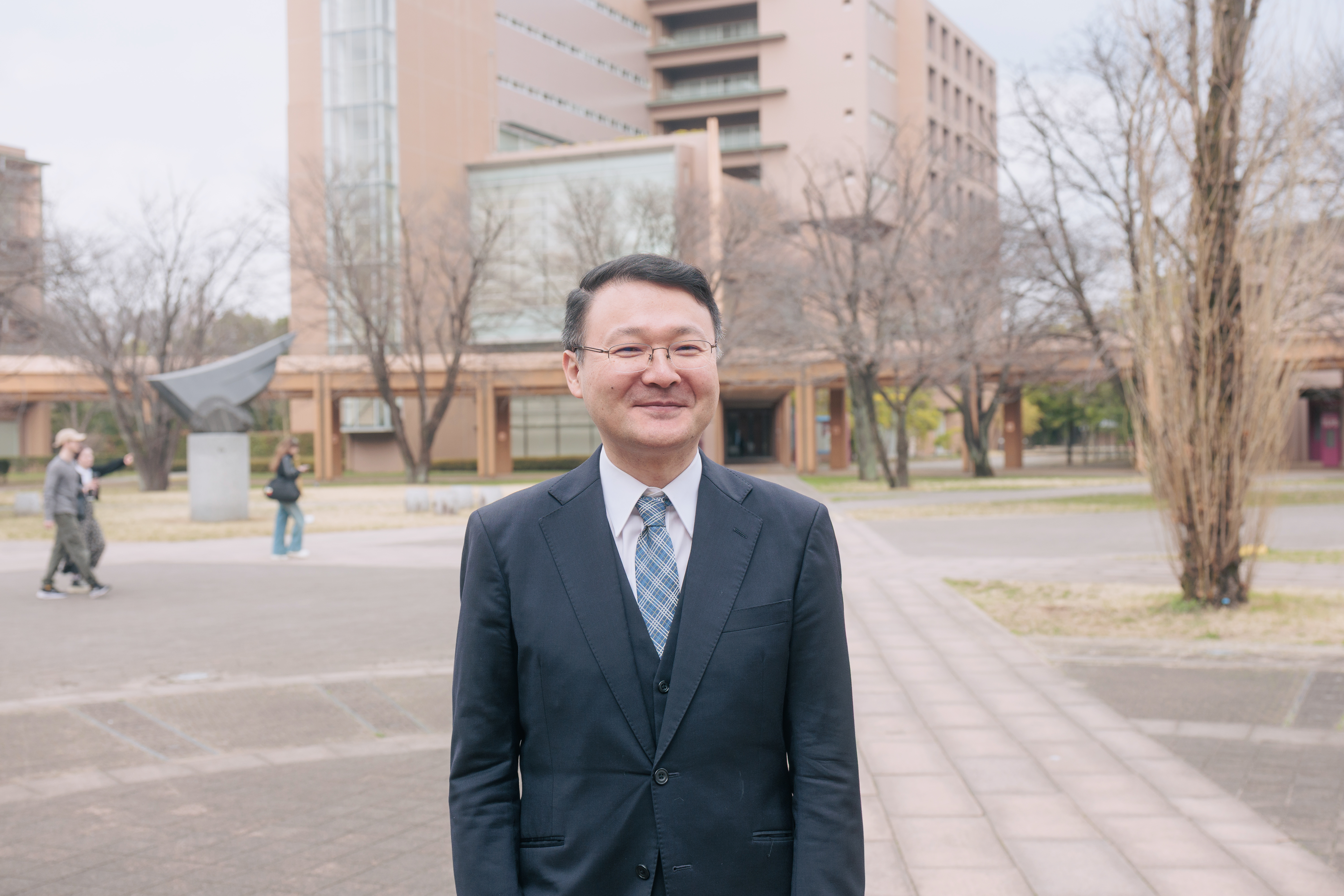
【ゲスト】 小野寺拓也先生
1975年生まれ.東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。昭和女子大学人間文化学部専任講師を経て,現在,東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授。専門はドイツ現代史。著書に『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」』(山川出版社),訳書にウルリヒ・ヘルベルト『第三帝国――ある独裁の歴史』(KADOKAWA)などがある。
「感情」は、複数の領域をつなぐ重要なファクター
滝口: 先生が現在どのような研究に取り組んでいらっしゃるか、改めてお伺いしてもよろしいでしょうか。
小野寺先生: 私の研究領域は主に4つあります。
1つ目は「ナチズム研究」。ナチズム全般について検証し、日本社会に適切に紹介する取り組みです。
2つ目は「エゴドキュメント研究」で、個人の手紙や日記、証言といった一人称の記録(エゴドキュメント)を大量に読み、分析することで歴史を構築する研究です。特に、第二次世界大戦中のドイツ兵士の手紙から、なぜ最後まで戦い続けたのかを分析しています。
また3つ目は、「歴史教育をめぐる研究」。高校で2022年から始まった新科目「歴史総合」の教科書執筆に携わっており、単なる暗記ではなく、資料を基に問いを立てて自分で考える歴史教育を重視しています。
そして4つ目が「感情史研究」です。クリスマスを例に、ナチスがどのように人々の感情を操作しようとしたのか、それが本当にうまくいったのかといった感情の側面からの歴史研究をしているのですが、研究を進めていくうちに4つある研究領域のすべてが「感情」によって繋がっていると考えるようになりました。

十河: 感情によって繋がっているというのは、具体的にどういうことでしょうか。
小野寺先生: 例えば、人々がナチ体制を支持した理由を考える際、反ユダヤ主義や経済的インセンティブといったイデオロギーや経済的合理性だけでは説明できない部分が多くありました。そこに「感情」というファクターを入れることで、ナチズムのメカニズムがより深く理解できると考えるようになったのです。
歴史教育においても、正しい知識を授けることが大事だと一般的には思われていますが、人間は正しい知識を学べばきちんと過去を理解できるという前提が最近疑われるようになっていて、「歴史意識(歴史的事象を人々が理解する際にベースとなるイメージ)」が注目されるようになってきています。歴史意識とは、ある歴史を「自分にとっては嬉しいことだ」とか「こうあってほしい」というように、それが事実かどうかとは別にして、個人や集団が感情的にどう捉えているのかということです。私の共著書『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』に対しても、「是々非々でなければならない」「白と黒だけではない世界があるべき」といった感情から、ナチスを否定的に評価することに抵抗を感じる反応がみられました。そうした人間の感情を意識しないと、人々を動かすことは難しいと痛感し、教育においても感情が大事だと考えるようになりました。現在の私にとって、感情史はあらゆる研究をつなぐ扇の要のような存在になっています。
感情史に着目した背景

十河:先生が感情史に着目された具体的なきっかけは何だったのでしょうか。
小野寺先生: それは間違いなく、東日本大震災です。震災時、(放射性物質への不安感が高まったことから)福島県産の農作物が全量検査されていて、その事実を知っている人ほど福島県産を避けるという調査結果が出ています。ですが、これは合理的に考えると本来逆になるはずです。この現象はコロナ禍でも繰り返されましたが、人間は情報を持つほど正しい判断をするとは限らず、むしろ逆の判断をすることもあるという現実を示しています。不安な人は情報を集めますが、その情報がエコーチェンバー化(注:自分と似た意見や価値観を持つ人々とばかり情報をやりとりすることで、自分の考えが「正しい」「多数派だ」と思い込んでしまう現象)してさらに不安を増幅させることが多々あるということです。この経験から、「話せば分かる」という研究者が前提としていた考え方が通用しない現実を突きつけられ、感情を重視しなければ研究が進まないと強く考えるようになりました。
滝口:確かに、日本の場合は3.11のタイミングでこうした不安が顕在化したように思います。アメリカの場合は、9.11同時多発テロが同様のきっかけになったのでしょうか。
小野寺先生:感情史という言葉ができたのは1980年代ですが、19世紀末から同様の研究をしている人はいたので、特定の単一のできごとによって急に始まったわけではなく積み重ねの結果だと思っています。ただ、3.11や9.11のようなインパクトのある事象によってそれが加速したことで、21世紀に入ってから感情史に関する研究機関やジャーナルが次々と設立されるなど研究が活発化していったのでしょう。
感情史の現状

十河: 感情史の定義は、歴史や過去のできごとを客観的な視点からだけでなく、感情の側面を含めて捉え直すことという理解でよろしいでしょうか。
小野寺先生: 私はそのように理解していますが、感情史というジャンルはまだできたばかりで「こういう学問です」と明確に定義できる段階には至っていないので、人によって問題意識が異なっているところがあります。学会や専門ジャーナルが確立されていくとジャンルとしての地位が固まっていくのですが、欧米で雑誌ができたのもここ数年のことですし、特に日本ではこれからという状況です。
滝口: 現状は欧米を中心に研究されているのですね。現在の感情史研究で「ホットなテーマ」はありますか。
小野寺先生: 今はまだ特定の流行や中心があるわけではなく、個々の研究者がそれぞれのテーマに「感情」というファクターを導入し、多様な実証研究を積み重ねている段階ですね。例えば、動物と人間の感情、国際人道法における共感、政治運動における無気力という感情、歴史教育における共感の動員など、本当に様々です。
十河: 感情という新たな視点を得て、皆さんが研究の幅を拡張されている段階なのですね。
ちなみに、これまでの歴史研究において、感情のように別の視点が持ち込まれたことで大きな変化がもたらされた実例はあるのでしょうか?
小野寺先生:過去30年で、歴史領域を最も大きく変革した概念は間違いなく「ジェンダー」です。
今まで世代論など色々な視点が持ち込まれましたが、今の歴史研究において、また政治・経済・法律などの隣接領域についても、ジェンダー抜きの研究はほぼ無理と言っていいでしょう。たとえば私は、軍隊は男性の組織なので「男らしさが軍隊の行動原理にどう影響を及ぼしたのか」という視点で研究していますが、もはやジェンダーという視点がなければ研究の説得力がないという状況になっています。
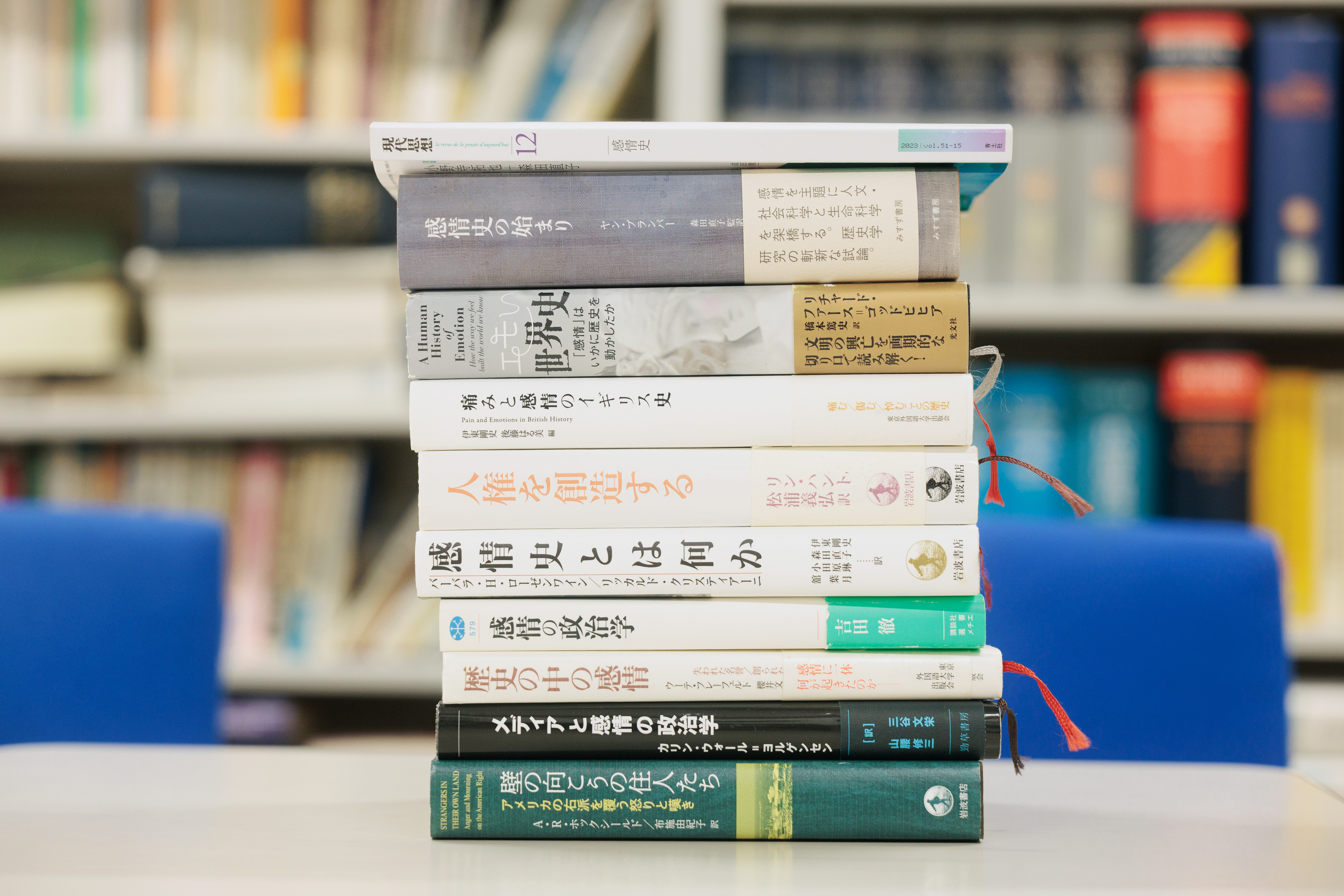
滝口:ジェンダーが人文系の研究にそこまで大きな変化をもたらした理由はどこにあるのでしょうか。
小野寺先生:やはり男性と女性、LGBTQも含めて、社会全体に影響を及ぼす視点であるということが大きいでしょう。加えて80年代以降、女性の社会進出などもあってジェンダーについて人々が意識せざるを得ない社会になってきているという社会の変化によるところも大きいと思います。
感情も同様に、人間存在の本質的なものであり社会全体に関係するものですよね。かつ、9.11や3.11、トランプなどを経てポピュリズムが台頭してくるなかで、これをなんとかしたいという社会の変化と要請もある。その意味で、ジェンダー以降30年ぶりくらいに学問領域を根本的に変えうるポテンシャルがあると思っています。
十河:確かに、感情は私たちの誰もが備えているものですし、政府や企業が感情をあおるようなことも増えていますよね。
小野寺先生:日本の歴史研究においては、ジェンダーや感情史のような欧米の概念を引っ張ってきて日本を理解することに対して「ミーハーな流行りものに乗りたくない」といった抵抗感を持たれることもあります。しかし私は、外来かどうかに関係なく「概念」は重要なものであり、物事を多角的に捉えるための「足場」や「補助線」のようなものだと考えています。補助線があることで、今まで見えなかったものが見えてくることがあるわけです。社会で不正が起きたときも、「人権」という概念=抵抗の拠点があれば「それはおかしい」と言えますが、概念をなくしてしまえばただただ流されてしまうだけかもしれません。そうならないために、概念を教えることは教育の重要な役割だと考えています。

2013年 博報堂入社。管理部門を経て、生活総合研究所で消費行動を中心とした生活者研究に従事。その後、マーケティングプランナー・ディレクターとして自動車や商業施設・消費財などの様々な領域のマーケティングを担当、2024年より現研究所設立に伴い現職。生活者の新しい潮流・消費行動に関する研究やソリューション化に取り組んでいる。
今読んで欲しい「生活者発想・未来洞察」に
関する記事
関連記事
- 生活者発想・未来洞察2025.08.15【連載】 なぜ『感情ハック』を研究するのか感情ハック 連載vol.0
- 生活者発想・未来洞察2025.08.15【連載】感情が“資本”になる時代に─感情と社会のこれから(前…感情ハック 連載vol.1
- 生活者発想・未来洞察2025.10.03【連載】感情の時代をどう生きるか──現代社会の課題と感情史の…感情ハック 連載vol.2





